 |
 |
 |
「すべての人が健康で、そして幸せであるように」
ある女性のそんな思いから、私たちの女子栄養大学は生まれました。
その人の名は香川綾。女子栄養大学の創設者であり、日本の現代栄養学の礎を築いた「栄養学の母」ともいえる女性です。
香川綾が残した業績は多岐にわたります。その中から、みなさんもよく知っているものをあげれば、たとえば、計量カップと計量スプーンがそうです。意外でしたか?
明治や大正の時代には、料理は誰にでも作れるものではありませんでした。しょうゆや塩の加減は「料理人の勘」、火を通す時間は「料理人の経験」、さらに味の決め手は「隠し味」や「愛情」でと、すべてがこの調子。現代のレシピでは当たり前の「塩小さじ2分の1」や「煮込み時間20分」といった表現はなく、「ほどほどに」や「火が通ったら」などの表現が使われていました。これでは料理の初心者が、経験豊富な料理人と同じような、おいしくて健康的な料理を作るのは無理な話です。
それを、素材や調味料を計って数量化し、料理の手順をわかりやすく文章にして、誰もができるようなレシピを初めて作りあげたのが香川綾だったのです。計量カップと計量スプーンはそのために必要な道具だったのです。
でも、それは彼女の業績のほんの一部に過ぎません。
明治生まれの綾の世代では、栄養学の重要性はほとんど認識されていませんでした。そのために、脚気をはじめとした栄養のアンバランスや無知から生じる病気が、多くの日本人を苦しめていました。
そんな時代に青春時代をおくった綾は、女性が外で働くことすら珍しかった当時に女性医学者として栄養学の研究に没頭し、戦後は栄養学部がある大学の創立に情熱を傾けたのでした。
道のりはなまやさしいものではありませんでした。でも、綾にはそれをやり遂げるだけの信念がありました。「すべての人を健康に。そのためには栄養学を普及しなければ」という、強い信念が……。
その情熱はいったいどこから生まれたのでしょうか? 日本人の健康のために生涯を捧げた綾の人生を、これから振り返ってみましょう。 |
|
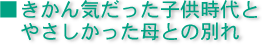 |
 |
明治32年、和歌山県本宮村に綾は生まれました。「女も勉強すれば偉くなれるご時世だ」が口ぐせの、当時としてはひらけた考えの父、物静かでやさしい母、そして仲のよい兄弟や姉妹たち。
そんな環境で育った綾は、幼い頃はきかん気でした。一度こうと思ったら、叱られようがお灸をすえられようが、泣きもしないで意思を通す子供だったようです。
食生活の大切さは、生活のなかで自然に学んでいきました。
綾の母親は料理上手な女性でした。
冷蔵庫などなく、食材も豊富ではない時代でも、綾の母は新鮮な魚ですしを作ったり、とれたての野菜を煮たりと、心のこもったおいしい料理をこしらえました。幼い日の綾は、母親がてぎわよく料理するようすを「まるで手品みたい」と、うっとりとながめていました。
10歳頃には、こんなこともありました。母の焼いたまだ熱いクッキーを頬ばりながら、綾はふと涙をこぼしそうになったのです。
うちはいいなあ。頼もしい父がいて、きょうだいは仲良し、そして自分たちを温かく見守ってくれる母がいる……。
母の心のこもったクッキーの味が、家庭のあたたかさや愛情を注がれて育つ幸せを、幼い綾に伝えたのでした。
けれども、そんな幸せも永久には続きませんでした。
大正3年、綾14歳。実家を離れ、和歌山で店を開いていた兄のもとに身を寄せていた時のこと。2月のある日、母の死の知らせが届いたのです。
肺炎で1週間前から入院していたものの、綾が見舞いに訪れた時は、見舞客と談笑するほど元気でした。なのに、なぜ!?
突然の母の死は、まだ14歳の綾には、すぐには受け入れられないショッキングな出来事でした。実家に戻っても、大好きな母はもういません。あれほど楽しかった食卓もともしびが消えたよう。家族中が黙りこくって食べる食事は、どんなご馳走を食べても、砂をかむような気がしました。
のちに父親は再婚しますが、その女性は料理が好きではありませんでした。食事は店屋物をとるか、簡単にすませるだけ。綾の目から見ても父は寂しげで、食事ひとつでこれほど家庭の雰囲気が変わることが、綾には大きな驚きでした。 |
|
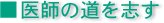 |
 |
早すぎた母との別れは、愛情のこもった料理の大切さを綾に教えると同時に、将来の道のりにも大きな影響をあたえました。
「あんなに元気だったのに死ぬなんて、医者の誤診だ。そのために手遅れになったのだ」
母の死後、綾はこう思いつめました。
そして、「もし自分が医者だったらお母さんを助けられたかもしれない。自分のように母を亡くし、小さな子が悲しむことのない世の中にしたいそのためには医者になるしかない」
そう考えるようになったのです。
けれど、当時はまだ女医はほとんどいなかった時代。父親にも反対され、綾は一時は教師の仕事につきます。けれど心の中では、医学への夢は捨て切れませんでした。
そして大正10年、3月。ついに家族を説得し、上京。東京女子医専を受験し、トップの成績で合格します。この時、綾は22歳になっていました。
念願叶っての医専生活は、生理学、組織学、解剖学など、どの授業も興味深いものでした。5年間、綾は夢中で勉強し、卒業後には東大の島薗内科に入局することになりました。
ただ、内科に入局したとはいえ、男女差別のはげしかった時代のこと。綾の身分は「介補」といって雑役係のような役回りで、しかも無給。そんなきびしい条件でしたが、それでも綾は懸命に働きました。そして、その島薗内科での勤務時代に、運命の転機を迎えることになるのです。 |
|
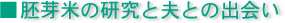 |
 |
綾が島薗内科に入局したころ、日本には脚気が蔓延していました。当時の食糧事情は劣悪で、ビタミンB1欠乏症による脚気患者の多さに、「脚気が国をほろぼす」とまで言われていました。脚気治療の研究は、島薗内科でももっとも大切な課題でした。
そんな中、島薗医師が綾にあたえた研究テーマは、「ご飯の炊き方」という、実に意外なものでした。
学術的な文献などもちろんありません。どう研究に取り組めばいいのか見当もつきませんでしたが、綾は、ともかく研究室に調理台を作りました。そして、米の吸水量から米を洗う時の水の温度、水に浸す時間の長さ、炊く時の水温や水の量、火加減、ふたの重さ、炊きあがった時の米の増え方などを、ハカリやメジャーで計測し、くる日もくる日も、綾はご飯を炊き続けたのです。
2ヶ月の実験ののち、綾は「胚芽米の炊き方」という論文をしあげました。そんな綾に、「日本の食品のビタミンB含有量とそれに及ぼす調理の影響」「胚芽米の作り方とその栄養価」「病院給食の改善」と、島薗医師は次々に研究テーマをあたえていきました。
これらの研究でわかったのは、胚芽米にはビタミンB1が豊富だということ。白米に精米すると、ビタミンB1はほとんど失われてしまうこともわかりました。ビタミンB1は脚気を防ぎ、治療にも使われる大切な栄養素。こころみに胚芽米を病院給食に取り入れてみると、脚気患者が薬も使わずに回復したのです。
「主食を白米から胚芽米にかえるだけで、脚気の治療ができる。脚気を未然に防ぎ、病気への抵抗力を高めることもできる!」
食事だけで健康を取り戻せるという発見に、綾は感激にふるえました。のちに栄養学に人生を賭けることになるのは、この島薗内科勤務時代の体験があったからこそなのです。
研究に追われる日々でしたが、合間に料理学校にも通いました。料理法がわからなければ、病院給食の研究もできないからです。
けれど、いざ授業をうけると、綾にはわからないことだらけでした。煮込む時間は「火が通るまで」、調味料は「ほどほどに加え、味見しておいしいお味に」。分量や加熱時間、調味料の割合などは、どれも秘伝とコツだらけで、習った料理をもう一度作ろうと思っても素人には無理なのです。
「『ほどほどに』や『ちょうどよい加減』を、うまく人に伝え、誰もがおいしい料理を再現できる方法はないかしら?」
綾はそう考えました。料理人の手順を目で見、舌で味わいながら覚えるのも方法ですが、誰もが目安にできる何かがあれば、多くの人がおいしく、栄養豊富な料理を味わえます。
考えたすえ、綾は料理を数量で表現することを思いつきました。
「胚芽米の炊き方の研究と同じように、分量や火加減、調理時間、調味料の割合を計算し、記録すれば、いつでも誰でも同じ料理を作ることができる!」
さっそく綾は、研究室になべや釜、時計、温度計、メスシリンダーなどを準備しました。そして、料理学校で習った料理をその日のうちにもう一度研究室で作り、記録をとる作業を始めたのです。
とても手のかかる作業でしたが、これをひと月、ふた月と続けるうち、綾はあることに気がつきました。それは、「味の決め手は塩分にある」ということです。
人の体液は0.9パーセントの塩分を含みます。食事での塩分摂取量は、この人の体液の塩分濃度のバランスを保てるものでなければなりません。しょっぱいものを食べると喉が渇くのは、体液の塩分濃度が濃くなったために水分で薄めようとする生理的な要求なのだ、こう綾は気づいたのです。
食塩の量が決まれば、甘みや酢とのバランスなど、ほかの調味料の割合もしぜんに導き出されます。これらの発見をとおし、綾はこう確信しました。「料理を初めて習う人でも、調味量のわりあいが数字であらわされていれば、すぐれた調理人が作る料理の80パーセントくらいは再現できる」と。
「料理を数字で表すおもしろい女医がいる」
こんな評判は、またたく間に広がりました。
栄養の知識が普及すれば、すべての人の健康のために大きく役立ちます。そう考えていた綾は、招かれればどこにでも出向き、栄養の話、食生活の指針について、一生懸命伝えてまわりました。
婦人会の会合で話すうち、とっさの思いつきで「主食は胚芽米、副食は魚一、豆一、野菜が四」というスローガンが生まれ、それが一般家庭に広く浸透して食生活の指針になるという出来事もありました。
これらの経験を通し、綾はこう考えるようになりました。「命の源は栄養にある。生きている限り、人は食べなければならないが、食べ方を間違えれば病気にもなる。正しい栄養知識を広め、病気を予防することが自分の使命なのではないだろうか」。
病気を治す医学に従事するより、栄養改善運動を一生の仕事にし、人々の病気を未然に防ぎたい。そう綾は思い始めたのです。 |
|
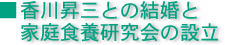 |
 |
東大の島薗内科勤務時代のもうひとつの大きな出来事は、香川昇三との出会いでした。
2人が出会ったのは、綾が入局したその日、大正15年5月のこと。当時東大内科では、新人は先輩に臨床指導を受けることになっていましたが、綾を指導する担当が、昇三だったのです。
白衣に金縁眼鏡のいでたちの昇三のことは、最初は「おとなしそうな人」としか思わず、結婚することになるとは夢にも思いませんでした。が、昇三と綾は、興味の方向や人生の目的がぴったりと一致していました。昇三もやはり、綾と同じように病気を防ぐ学問として栄養学に熱心に取り組んでいたのです。
恋愛関係というより、むしろ同志的な感情で2人は親しくなっていきました。そして、入局して5年後の昭和5年の3月。綾は島薗医師から昇三との結婚を勧められたのです。
「もっと研究を続けたい」と迷いもありましたが、「結婚はチャンス、仕事は一生」という島薗医師の言葉に心は決まりました。そして、昭和5年5月、2人は結婚。
その後も東大の研究室に通っていた綾ですが、昭和6年に長女を妊娠したのを機に正式に退局。医療の現場から退くことになりました。
けれど、人生はふしぎです。この妊娠と退局をきっかけに、綾は「人々の健康のために栄養学を普及したい」という夢を追って生きることになるのです。
島薗内科を退局してからの毎日は、それまでの忙しさがうそのように、のんびりした日々でした。昇三の論文を清書したり、昇三の帰宅後に栄養学の研究の話を聞いたり、週末には井の頭公園や深大寺などを親子でピクニック…。この頃が生涯でいちばん落ち着いて幸せなときだった、と綾は著書『栄養学と私の半生記』にしるしています。
けれど、栄養学への夢をもつ綾は、のんびりした日々に埋もれることはできませんでした。次々にさずかった子供たちを育てながら、「料理を計量化することの大切さをもっと世間につたえたい」という思いが、日に日にふくらんでいったのです。
その頃は、まだ医学界ですら、栄養学は軽視されていました。栄養学と医学が車の車輪のように支え合い、助け合うには、まだまだ長い年月がかかるはず。そんな時代に栄養学の仕事を始めることは、時期が早いという迷いもありました。
また、当時は1人の女性としても、長女の芳子が2歳、長男靖雄1歳、そして次男の恒雄がおなかにいるという時。仕事を始めて子供たちのことがおざなりになっては、という母親ならではの心配もありました。
この時も、綾の迷いを払いのけてくれたのは島薗医師でした。「病気を治す医師はたくさんいても、未然に予防して病人を作らないことのほうが大切だ。それなのに栄養改善を手がけて病気を防ぐ医師がいないのは嘆かわしい」という島薗医師の言葉は、綾や昇三の考えとまさしく一致したものでした。そして、綾は、昭和8年、夫昇三とともに、家庭食養研究会を設立したのです。
自宅の10畳間を改造して作った教室で、約20人の生徒を集めてのささやかなスタートでしたが、綾の胸には、「いつかは栄養学の大学を」という大きな目標がありました。それが実現すれば、栄養学はもっと浸透し、人々の健康に寄与できます。そんな夢を抱いての綾の最初の挑戦が、家庭食養研究会の発足から始まったのです。
家庭食養研究会での活動はユニークなものでした。
綾は、まず一流の料理人を講師に招きました。フランス料理、日本料理、懐石料理、家庭料理、中華料理など、いずれも当時の最高水準の料理人ばかり。その料理人たちの料理にものさしをあて、計量化する……。これが、家庭食養研究会が最初に手がけた実験です。
まず、綾たちは講師が作る献立にあわせ、材料や調味料を多めに用意し、すべての重量を計っておきます。講師たちはその材料で料理をしますが、綾や生徒は講師が調理するそばから材料や調味料の残りを測り、最初の分量からそれを差し引けば、講師が調理の手順のどのプロセスで、何をどれだけ使ったかわかるというわけです。
火加減も弱火、中火、強火の3段階で記録をとり、加熱時間はストップウォッチや時計で計測しました。調理の手順や方法、盛り合わせ方なども、できるだけくわしく記録を取りました。
こうしてできあがったのが「料理カード」です。ここには材料や調味料の分量、調理の順番や火加減、調理時間などがしるされ、この通りに料理をすれば、誰でも一流の料理人と同じ料理がほぼ再現できます。
料理の技術は、それまでは料理人のもとで何年もかかって習得するしかなかったものでしたが、それを全国のどこにいても身につけられるという、まったく新しいシステムを綾は生み出したのです。「すべての人を健康に」という夢に向かっての大きな大きな前進でした。 |
|
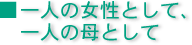 |
 |
綾が料理カード作りに没頭していた時期は、ちょうど子育ての時期とも重なっていました。
長女、長男、次男、三男と、次々に子供に恵まれ、忙しく働くかたわら、綾は4人の子供たちの母親でもあったのです。
昭和の初めは、疫痢や肺炎の流行で乳児の死亡率が高かった時期。そんな中で綾がいちばんに考えたのは、なにより子供を殺さないということでした。そのためには、家庭と職場が近くにあり、仕事をしながらも子供たちに目が届く環境が必要でした。
けれど、いくら住居と職場が近くても、4人を育てながら働くのは並大抵ではありません。なにしろ子供たちはまだ幼く、夜中の授乳やおしめの取り替えなどで、綾の睡眠時間も4時間がせいぜいでした。
けれど、苦労ばかりではなく、子供たちは幸せもくれました。『栄養学と私の半生記』にはこんな記述があります。「授業の合間を見ては家の雑用を片づけ、時間があいている時は編み棒を動かしていました。教室から講義の声が聞こえる園長室で、あるいは講演に行く汽車の中で、男の子でも女の子でも着られるように、いつも白い毛糸でセーターや靴下を編んでいました。学園のことも栄養学のことも忘れて、子供が成長していく様子だけが目に浮かんで、私の幸せなひとときでした」
ワーキングマザーとしての葛藤もありました。長女が5歳頃のこと。ある日、綾が学校の休憩時間に家に戻ると、上の子供たちが末っ子をふとんに巻き、階段の上から転がして遊んでいたのです。
驚いた綾は子供たちを座らせ、「お父さんもお母さんも仕事でかまってやれないけど」と話しました。叱りながらも「幼い子供たちにどうすれば仕事を持つ母の生き方を理解してもらえるだろう」と、吐息がもれました。
末っ子の達雄が学校のまわりを「お母さんがいない」と探し回っていたと聞いた時も、胸が痛みました。
それ以来、どんなに忙しくても子供たちと過ごす時間を作ることを、綾は心がけました。子供たちを教室に座らせて授業をしたこともありました。子供たちが幼稚園や学校から帰ったら、順番に抱っこし、童話を読んであげたり宿題を見てあげてから住まいに帰らせるなど、母親として精一杯の努力をしました。早く死に別れたとはいえ、綾自身は愛情深い母親に育てられました。同じ愛情を子供たちに注ぐことを、綾もやはり片時も忘れなかったのです。 |
|
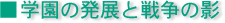 |
 |
一方、家庭食養研究会では、雑誌を作る話が持ち上がっていました。受講生にくばる料理のテキストを毎回作るのはたいへんなので、活版印刷の雑誌を作ろうということになったのです。昭和10年の3月のことでした。
誌名は『栄養と料理』に決定。昭和10年5月には、創刊号200部が完成しました。料理雑誌が珍しかったこともあり、創刊号は好評で、2号目、3号目と続くことになりました。
さらに、昭和12年からは家庭食養研究会は「女子栄養学園」と名称をあらため、全国から学生を募集することになりました。続いて昭和16年には、現在も女子栄養大学の駒込校舎のある駒込に校舎を新築。こうして綾と昇三が夢に描いた、健康のための栄養学の普及は、少しずつ形になっていったのです。
けれど、こうして綾が栄養学の普及につとめた時代は、不穏な時でもありました。女子栄養学園がスタートした昭和12年の7月7日には日中戦争が始まり、昭和16年にはついに太平洋戦争が勃発。食糧事情は年々悪くなり、国民の健康状態も心配されるようになってきました。
昭和18年ころになると、体が弱いため徴兵されなかった昇三も、栄養学の研究一筋ではすまなくなってきました。軍の要請で、全国の軍隊の基地に栄養指導にかり出されるようになったのです。
この頃、昇三はよくこう語りました。「こんな世の中、どちらかが1人になっても目的は一致しているのだから、生き残った者が2人の意志として仕事を続けよう」と。昇三も綾も明治の人間。戦争という非常事態の中でも、自分の学問を人のために生かすことをいちばんに考えたのでした。
そして、戦火がいよいよ激しくなった昭和20年、学園は群馬県大胡町に疎開することになりました。が、疎開を目前ひかえた4月23日、たいへんな試練が待ちうけていたのです。
それは、空襲による学園の焼失という、予想だにしていなかった出来事でした。 |
|
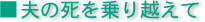 |
 |
学園の焼失後、学生たちは一時浦和に疎開し、5月になると、順次群馬県、大胡町に疎開を始めました。
しばらくは、夫婦は別居生活です。綾は大胡町で講義を始めなければなりません。一方の昇三は、まだ浦和にいる学生たちや子供たちの世話で浦和に残ることになったのです。
が、そんな別居生活も、7月16日にはひとまず終わり。この日の正午頃、昇三はひさしぶりに綾のもとに到着し、親子水入らずの時間を楽しんだのです。1週間前まで広島の大竹基地に食事指導に出向き、帰京して学習院の講義をすませてから駆けつけた昇三は、疲れのせいか顔色はすぐれませんでしたが、綾や子供たちに会い、ほっとしたようすでした。
けれど、わずかな時間を過ごしたのちは、また夫婦別々です。綾や子供たちがいるのは第一寮、昇三は隣村の第二寮の監督のため、夜はそちらで過ごすことになっていました。
3時すぎには、綾と長男の靖雄が昇三を見送り、3人は第二寮まで40分の道のりを並んで歩きました。のどかな道を歩きながら、昇三は「静かだねえ。ここなら、安心して勉強ができる」と、なんども繰り返しました。
そんな昇三のようすが、忘れられない思い出になるとは、その時の綾には想像もつかないことでした。
夜には、雨が降り始めました。
びしょぬれの第二寮の助手が綾を訪れたのは、12時くらいのこと。昇三が倒れたのです! 医学の知識のある綾は、助手の話からすぐに脳溢血だと判断しました。
「疲れていたはずなのに、学園の焼失で勉強が遅れている焦りがあったのだろう。戦争中で食糧難だからこそ、栄養学を国民の役に立てたい願いも強かったのだろう。そのために無理をしたに違いない……」。第二寮につくとすぐに講義をし、夕食後にも3時間も学生たちと話していたと助手から聞かされ、綾は、闇の中を歩きながら昇三の心中をはかりました。
第二寮に到着したのは、夜中の2時をまわったころでした。昇三にはまだ意識があり、綾の見立てと同じく、「脳溢血だね」とつぶやいたと言います。自分たちが医師であることを、この時ほど悲しいと思ったことはない、と綾は記しています。
処置してあげたくても、医療器具はもちろん、電話すらない場所ではどうにもなりません。せめて砂糖水でも、と、くず湯を飲ませると、「おいしい」と昇三は応え、うとうと眠り始めました。
そして、翌17日、午後2時47分。昇三は51歳の生涯を終えたのです。
同年8月15日には、日本は敗戦。この年は、綾にとって思い出すだけで胸が締め付けられるような辛い年になりました。
戦争が終わったところで、綾の苦労が終わったわけではありません。駒込の校舎は焼け野原、その上、夫の相続税がのしかかり、預金は封鎖され、と苦しいことばかりです。
けれど、綾は学園の再建をあきらめませんでした。駒込の校舎を再建するだけのお金はありませんでしたが、家庭食養研究会を開いた駕籠町の建物を修理し、2部屋ばかりの教室を用意して、昭和22年の4月には女子栄養学園をなんとか復興させたのです。続いて、たくさんの執筆陣の協力で、「栄養と料理」も再開させることもできました。
苦しい状況の中、綾を支えたのは昇三との約束でした。「こんな戦争の世の中、どちらかが1人になっても目的は一致している。生き残った者が2人の意志として仕事を続けよう」というあの約束が、綾を奮い立たせ、学園を守り抜く力をくれたのです。 |
|
 |
 |
戦争が終わり、海外の情報が入ってくると、綾は驚きました。戦時中は外国からの情報が入らず、食糧難のために研究も進められなかった空白の期間でしたが、その間に、栄養学は大きく進歩していたのです。
たとえば、人を動かすエネルギーは体内でどう作られ、どう使われるのか。こんなシステムもすでに解明されていました。カロリーや栄養素などの研究方法、検査方法も欧米では進歩していました。
もうひとつ綾を感激させたのは、戦後の医学の進歩でした。戦前の医学はドイツ式治療を目的とする医療が中心でしたが、戦後にはアメリカ式の予防医学が注目されるようになったのです。子供たちの健康を守るために学校給食の制度が整ったこと、予防接種の制度ができたことも、予防医学が普及したおかげです。
栄養学の知識をひろめ、病気のない社会を作りたいという綾の夢が、医学界の流れとようやく一致したのです。
綾の努力のおかげで、学園も着々と再建への道を歩みました。昭和24年に駒込校舎の再建、そして25年には、女子栄養短期大学の創立。昭和8年に家庭食養研究会を始めて以来、「いまに大学にしてみせる」と口癖のように言い続けてきたことが、17年の年月を経て、ついに実現したのです。
学園の再建とともに、綾の栄養学研究はまだ熱心に続けられていました。そのひとつが、計量カップと計量スプーンづくりです。
料理にものさしをあて、誰が作っても同じようにおいしく、栄養のある料理が再現できるようにする。これが、綾が追い続けてきたテーマでした。が、料理の世界では、グラムと匁のどちらも使われ、さらに戦後にはポンドやオンスも使われはじめて、そのままでは料理をはかるものさしがバラバラになり、料理教育が混乱する恐れが出てきたのです。
料理のものさしをメートル法に統一すること、そして、食材の計量で調味の割合を割り出す食生活を根づかせるにはどうしたらいいか、綾は考えました。その結果、計量カップと計量スプーン、そしてへらを作ることを思い立ったのです。
試作ののち、5cc、15ccの大小の計量スプーンと200ccの計量カップ、そしてすり切って正確に調味料をはかるためのへらが完成しました。これがあれば、しょうゆは小さじ1杯だと塩分は1グラム、塩小さじ1杯では塩分は5グラムというように簡単に塩分をはかれ、味つけも自由自在です。
今は、どの料理本でも大さじ1、小さじ1、カップ2分の1などと表記してあり、それをみれば誰でも間違いない味つけができますが、これも、綾の研究のおかげなのです。
一方、学園は、さらに新しい展開を迎えていました。昭和26年には、昼間働きながら栄養学の勉強をしたい人たちのために、夜間部を増設。そして、昭和36年には、4年制の女子栄養大学が設立されます。
文部省からの認可がおりず、当初は栄養学部ではなく、家政学部でのスタートでしたが、4年生の大学を作ることは綾の長年の夢でした。続いて昭和40年にはついに念願の栄養学部を開設。昭和44年には、女子栄養大学大学院の設立も認められたのです。
大学院設立の認可の通知は、ちょうど綾の70歳の誕生日を祝う席に届きました。綾の感激はそれだけにひとしおで、忘れられない思い出の日になったようです。
その記念の意味もあり、綾はそれ以来ジョギングを始めました。
「栄養学をみずから実行した見本として、いつまでも健康でありたい。いつまでも働きたい」
70歳を過ぎてからの挑戦には、そんな思いが込められていました。
|
|
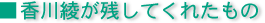 |
 |
平成9年4月2日午前9時25分、綾は永遠の眠りにつきました。98年の生涯でした。
料理カード、四つの食品群、計量カップ、計量スプーン、四群点数法など、綾はたくさんの財産を私たちに遺してくれました。なにより、いちばんのプレゼントは、誰もがおいしく、栄養のある料理を作ることができるようにしてくれたこと。料理の世界にものさしをあて、誰でも再現できるようにした努力が、今の栄養学や料理界の基礎を築いたのです。
けれど、料理を志す人なら、計量化だけが料理のすべてだと綾が考えていたわけではないことも知っておきましょう。
「栄養学と私の半生記」に綾はこう書いています。「私は、誰にでもおいしい料理が作られるようにと、調理の計量化を考案しましたが、だからと言って両技術がすべてだと思っているわけではありません。ただ機械的に量だけ計って作ってみても、献立作りから食事の時の雰囲気まで、あらゆる過程に心が行き届いていなければ、おいしい料理も健康づくりもできるものではありません。そこに食生活の難しさやたいせつさがあります」。
計量化で誰でも一定の料理を作れるようにすることに情熱を燃やした綾でしたが、「おいしい」「食べて幸せ」と思える料理を作るには、作る人の愛情や食卓の楽しさが大切だ──。
そんな考えを、綾は根っこのところでずっと持っていたのです。それを綾に教えたのは、早くに死別した母親でした。
もしかしたら綾は、彼女の母のそのメッセージをこそ、私たちに伝えたかったのかもしれません。 |
|